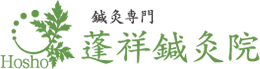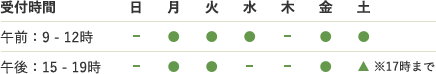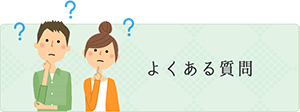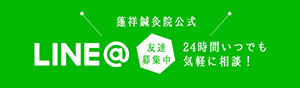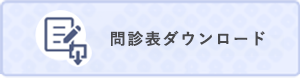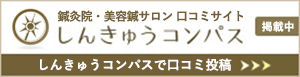【更年期でお悩みの方必見!】鍼灸師が教えるホットフラッシュ対策 名古屋市中川区高畑の蓬祥鍼灸院
ブログ
【更年期でお悩みの方必見!】鍼灸師が教えるホットフラッシュ対策
更年期障害によるホットフラッシュでお悩みの方へ。
突然起きるホットフラッシュはのぼせる辛さもありますが、大量の汗をかいてしまうため人の目も気になってしまうため、自分でできる対策がないか気になっていませんか?
今回は更年期によるホットフラッシュ対策について鍼灸師が解説していきます。
【更年期でお悩みの方必見!】鍼灸師が教えるホットフラッシュ対策

ご自身でも簡単にできるホットフラッシュ対策は以下の4つがあります。
- お灸によるセルフケア
- 自律神経を整える
- 大豆製品の摂取
- こまめな水分補給
【このツボは要チェック!】お灸によるセルフケア
まずは鍼灸師としてはお灸によるセルフ灸をおすすめいたします。
ボットフラッシュ対策としてのツボをネットで調べると色々な情報が出てきますが、よく紹介されているツボとしては以下になります。
- 百会
- 太衝
- 湧泉
- 三陰交
このあたりのツボがよく紹介されています。
この4つのツボも効果がないとは言いませんが、「更年期」という状態を東洋医学的に診ていくと先程紹介した4つのツボよりも効果的であり、要チェックなツボがあります。
更年期障害によるホットフラッシュでお困りの方にチェックしいていただきたいツボは以下の3つのツボになります。
- 気海:臍の下から指2本分くらい
- 照海:内くるぶしの下
- 太ケイ:内くるぶしとアキレス腱の間
この3つのツボで一番凹んでいるツボを選ぶようにしましょう。
私の経験上ではホットフラッシュでお悩みの方ですと、「気海」というツボがかなり凹んでいる方が多い印象があります。
個人差はありますが、ご自身でこの3つのツボの凹み具合をみてお灸をしてみてください。
自律神経を整える
ホットフラッシュは更年期による自律神経の調節がうまくいかないことが原因となっています。
そのため、自律神経を整えることも重要です。
- ストレス発散
- 適度な運動
- ヒリングミュージックを聞く
- 半身浴
- 腹式呼吸
- 規則正しい生活
このようなこと普段の日常生活でも取り入れることが大切となります。
大豆製品でホルモンバランスを整える
ホットフラッシュは更年期による自律神経の乱れが原因となりますが、更年期自体の原因は女性ホルモンであるエストロゲンの不足になります。
そのため、大豆製品を多めに摂るようにしましょう。
大豆に含まれるイソフラボンはエストロゲンを補う働きがあるため、大豆製品を食べることで女性ホルモンのバランスが整うことが期待できます。
- 毎食、豆腐を食べるのも良し
- 毎朝豆乳を飲むのも良し
- 運動しているのであればソイプロテインを摂るも良し
病院でのホルモン補充という選択肢をあまりとりたくないという方は大豆の力に頼ってみましょう。
水分摂取をこまめにする
ホットフラッシュでお悩みの場合でも水分摂取はこまめに行いましょう。
ホットフラッシュにより汗が噴き出てしまうと、汗をかかないよう水分摂取を控える方も中にはいらっしゃいます。
しかし、これでは脱水症状になってしまいます。
脱水症状を防ぐという意味でも水分補給はこまめに行うようにしましょう。
ホットフラッシュ対策として気になる漢方薬の効果

ホットフラッシュ対策として漢方薬を服用することを選択される方もいますが、効果が気になる方もいらっしゃるかと思います。
そのため、ホットフラッシュに対する漢方薬の効果についてもお話していきます。
手軽に始めるなら命の母から
ホットフラッシュ対策として漢方薬を始める場合、いきなり婦人科や漢方薬局へ行くという方法もありますが、まずは市販の「命の母」から始めるのが手軽と言えます。
手軽に始められるのはいいが実際に効果の方はどうか?ですが、やはり個人差があると言えます。
徐々に効果が出てきたという声もあれば、全然効果がないという方もいらっしゃいます。
最近ホットフラッシュがキツイので、命の母Aを飲み始めた。
最初は何だかイマイチだったけど、だんだん効いてきた。
あれ、ホンマ辛いねん。— lowlife (@sakiri001) November 22, 2021
注意していただきたいのが、命の母Aと命の母ホワイトの2種類ありますが、更年期の症状に対しては命の母Aが適しています。
命の母ホワイトは生理の不調の改善を目的として服用するものになるため、この部分で間違えないようにしましょう。
命の母Aと命の母ホワイトの違いについてはこちらを参照ください。
処方が間違っていれば効果はなし
ホットフラッシュ対策として病院や漢方薬局などで処方された漢方薬を飲んでもなかなか改善されないという方も実はかなりいらっしゃいます。
この場合は漢方薬の処方が間違っていることが原因となります。
よくある処方の仕方としてホットフラッシュだからこの漢方薬、更年期障害だからこの漢方薬というように症状や病名で漢方薬を処方してしまう場合があります。
しかし、この処方の仕方は大きな間違いです。
漢方薬も東洋医学となるため、更年期によるホットフラッシュがなぜ起きているのかを東洋医学的に分析し、一人ひとりにあった処方をしなければいけません。
東洋医学的な分析をするにあたっては問診以外にも脈診、舌診、腹診などを行う必要があるため、こういった東洋医学独特の手法を用いているかどうか患者側としてチェックしてきましょう。
※ただし、漢方薬局では脈診や腹診など患者さんの体に触れる行為が禁止されています。
更年期によるホットフラッシュ対策は鍼灸治療も検討ください

ご自身でのホットフラッシュ対策や病院での治療や漢方薬でなかなか改善されない場合は鍼灸治療もご検討いただければと思います。
東洋医学から考えるホットフラッシュ
西洋医学では更年期による自律神経の乱れが原因で起きるホットフラッシュですが、東洋医学では主に「陰虚」という加齢や体を冷やすための水が不足している状態になることで発症します。
陰虚の状態は体を冷やすための水が不足している状態であるため、相対的に体は熱傾向になってしまいます。
この熱がホットフラッシュとなって突然ののぼせや汗の原因となります。
さらに汗をかくことにより水分が不足してしまうため、こまめな水分摂取が必要となります。
ホットフラッシュに対する鍼灸治療
ホットフラッシュに対する鍼灸治療は先ほどの陰虚という体質を治療していくことになります。
陰虚に対しての鍼灸治療で使用するツボは先ほど要チェックのツボでもご紹介した、気海、照海、太ケイなどのツボの反応を診て鍼治療を行っていきます。
その他にも肝鬱化火というストレスが原因でホットフラッシュが起きている場合もありますが、この辺りは一人ひとり違ってくるため、ケースバイケースになります。
1時間おきに起きるほどの酷いホットフラッシュの場合は患者さんによってはその場で治療効果を実感できる方もいらっしゃいます。
治療期間としてはホットフラッシュだけであれば早い方で1ヶ月ほど、ホットフラッシュだけではなく更年期障害全体の治療となると3~6か月ほどが目安になります。
まとめ
ホットフラッシュは更年期障害の症状の1つではありますが、人によっては非常に不快な症状となってしまいます。
まずは自分でできる対策を試していただいたうえで、1ヶ月ほど経過しても改善の兆しが見られない場合は婦人科を受診したり、漢方薬局で漢方薬を処方してもらいましょう。
もし、それでも改善されない場合は鍼灸治療もご検討いただければと思います。
関連記事

更年期うつに対する鍼灸治療の症例
Contents 更年期うつに対する鍼灸治療の症例【50歳女性】更年期うつ発症から鍼灸治療を始めるまでの経緯自覚症状や生活習慣など弁証および治療について【考察】…

痩せるツボなど存在しない!ダイエットは運動と食事制限が基本です!
痩せるツボがあるのならぜひ知りたい方、ツボを押すだけで本当に痩せる効果があるのか知りたいと考えていませんか? 誰でもツボを押すだけで痩せることができるなら簡単に…

円形脱毛症の方に見られる共通の原因
こんにちは。 蓬祥鍼灸院の長谷川です。 本日は当院でも患者数が多い円形脱毛症についてのお話です。 円形脱毛症の患者さんの数が多く、色々な方の体を診てきてある「共…

【ポイントは体質改善】生理前のニキビ対策!鍼灸治療ができること
蓬祥鍼灸院の長谷川です。 生理前のニキビで悩んでいるため、何か対策としてできることがないかお悩みではありませんか? もし、あなたが生理前のニキビ対策をしているが…

不妊の原因の約50%は男性側にあり!男性不妊に対して鍼灸ができること
名古屋の蓬祥鍼灸院の長谷川です。 結婚して子供が欲しいが検査の結果男性不妊と分かりどうすればよいか悩んでいたり、どうすれば改善できるか知りたいと考えていませんか…
ご予約・お問合わせ
当院は完全予約制です。
施術中、問診中は電話に出られない場合がございます。時間をおいてからおかけ直し頂くか、お問わせフォームまたはLINEにてお願いいたします。
名古屋市 蓬祥鍼灸院の
適応疾患
-
婦人科系疾患
不妊症・更年期障害・生理痛・生理不順・冷え性・子宮内膜症など
-
神経系疾患
うつ病・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠症・神経痛・神経麻痺など
-
皮膚科系疾患
アトピー性皮膚炎・ニキビ・円形脱毛症・湿疹など
-
運動器系疾患
関節炎・リウマチ・肩こり・五十肩・腰痛・坐骨神経痛・腱鞘炎・頸肩腕症候群・捻挫など
-
循環器系疾患
心臓神経症・動脈硬化症・高血圧・動悸・息切れなど
-
呼吸器系疾患
気管支炎・喘息・風邪など
-
消化器系疾患
食欲不振・胃痛・慢性胃炎・潰瘍性大腸炎・逆流性食道炎など
-
眼科系疾患
眼精疲労・緑内障・仮性近視・結膜炎・かすみ眼・飛蚊症など
-
代謝・内分泌系
疾患バセドウ病・糖尿病・痛風・貧血など
-
耳鼻咽喉科系
疾患中耳炎・耳鳴り・難聴・花粉症・アレルギー性鼻炎・メニエール病など
-
泌尿器・
生殖器系疾患膀胱炎・過活動膀胱・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大症など